
日本経済、今こそ立ち上がらねばならぬ時
かつて日本は世界経済の中で、確固たる地位を築いておりました。昭和30年のこの頃、我が国のGDPは世界の約17.5%を占め、いわゆる経済大国としてその名を馳せていたのです。しかし、時は流れ、今日の日本経済はどうでしょうか。その占める割合は、わずかに5%にも満たないという厳しい現実が広がっています。何が原因だったのでしょうか。
振り返れば、昭和60年代後半のバブル崩壊がその端緒でありました。政府の経済運営における誤り、特に自民党政権の政策の失敗が大きな要因となりました。バブル崩壊後、政府は急激な金融引き締めを行い、経済に大きな冷え込みをもたらしました。金融機関は不良債権処理に追われ、市場からは資金が引き上げられ、経済は停滞の一途をたどったのです。
ここで注目すべきは、財務省が従来から推し進める「フロー重視」の経済運営にあります。いわゆる損益計算書(PL)を中心に、売上と経費の差額だけで経済の健全性を判断し、財政の健全化を目指した結果、実質的な経済成長を阻害してしまったのです。もちろん、負債が多いことは問題ですが、資産が十分にあれば、経済の健全性を保つことは可能であります。事実、日本は世界有数の債権国として、他国に多くの資産を貸し付けており、その点においては強みを持っていたのです。
ところが、現行の財政運営はその「ストック」を無視し、「フロー」のみに注目し過ぎました。PLの黒字か赤字か、ただそれだけを見て、国家の財政健全性を判断すること自体が誤りであったと原口一博議員は指摘しています。私たちは、単に数字だけに振り回されるべきではありません。我が国が保有する資産、債権の状況をしっかりと把握し、それに基づいた政策運営を行うべきなのです。
また、昭和30年において日本は、世界の経済において中心的な役割を果たしていたことは言うまでもありません。それが今や、世界のGDPに占める割合が急速に低下し、かつてはアメリカに次ぐ世界第2位の経済大国であった日本が、いまや中国の後塵を拝し、更にはドイツ、フランスに抜かれるのではないかという状況です。こうした経済的な後退を招いた要因の一つには、過度な緊縮財政と増税があります。
特に間接税である諸費税の増税は、いっきに2%や3%もの大増税を行った例は世界を見渡しても他になく、30年の間に3回もの2%以上の大増税を敢行したことによる経済の落ち込みはリーマンショックを遥かに超える過大な消費の落ち込みをもたらし、日本をデフレのどん底へと突き落としました。
さらに労働者の実質賃金は低下し続けており、これは経済政策の失敗を如実に示しています。過去にアベノミクスと呼ばれる政策が試みられましたが、その影響も決して十分とは言えません。増税や消費税の引き上げが、家庭の支出に直撃し、企業投資の減少を招いたことは否定できません。
このような状況を打破するためには、今こそ日本経済の根本的な改革が求められます。原口議員が訴えるように、財政運営の方針を転換し、国の資産や債権を最大限に活用した減税と積極的な政府支出、国債をさらに増やすことで成長軌道に乗せるべきであります。昭和30年にあったような活力と希望を、もう一度我が国の経済に取り戻すために、今こそその一歩を踏み出さなければならないのです。

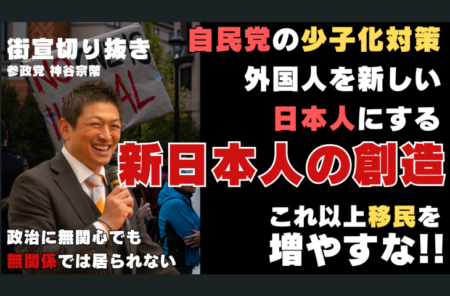



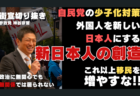
LEAVE A REPLY